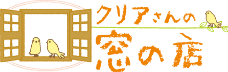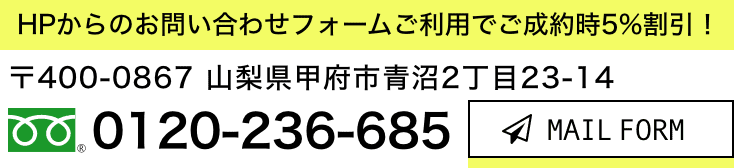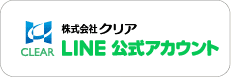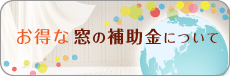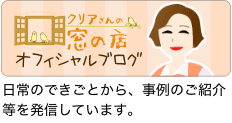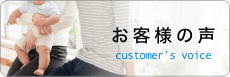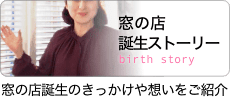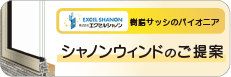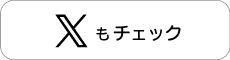二階さちえの「窓のコラム」
円窓のある銀座の宇宙船 〜 中銀カプセルタワービル 〜 *文と写真 二階さちえ
2021-07-16
まんまるの窓って、あまり見かけないですよね。おしゃれなお店やこだわりの住宅、あとは絵本に出てくる船やロケットでしょうか。
中銀(なかぎん)カプセルタワービルには、丸い窓が140個ついています。それは未来と自由を映す“宇宙船の窓”でした。
ビルが建ったのは1972年、場所は東京・銀座8丁目です。当時の名称は『中銀カプセルマンシオン銀座』その名の通り、ビジネスパーソンのセカンドハウスやホテルライクな宿泊施設、都心の別荘、小規模オフィスが主な利用目的でした。
カプセルと呼ばれる積み重なった箱は、エレベーターが通る中央の柱にボルトで留められ、独立した部屋になっています。特異な外観は多くの人が「レゴブロックを組み立てたみたい」と感じるでしょう。そのとおり。ブロックや積み木のように“取り替えられること”が最大のテーマだったのです。
建築家・故黒川紀章は『メタボリズム(新陳代謝)』という建築思想のもと、このビルを設計しました。一度できたらそうは変えられない従来の建物と違う、使い方や時代に合わせて生き物のように変化する建築をつくる考え方です。カプセルタワーはこの思想が形になった、世界的でも稀な建築として知られています。
自由で斬新、時代の先を行くスピード感にあふれた“マンシオン”は、銀座という立地のよさも手伝って売り出し後約半年で完売。価格はカプセルひとつ約340万円ほどだったそうです。
当時は大阪万博の2年後で、科学技術の発展や未来・宇宙への夢が高らかにうたわれる高度経済成長期の終盤でした。大都市を24時間動き回って仕事をする、今日『デジタルノマド』と呼ばれるようなライフスタイルを自認していた人々にとって、カプセルタワーがこの上なく魅力的に見えたのは想像に難くありません。
カプセルが傷んだり老朽化したら、スポッとはずして入れ替える。新品はよそでつくって運んでくるからトラックに載る大きさにしよう。冗談ではなく本当の話です。幅約2.5m、奥行き約4m、天井の高さ約2.2mのサイズはこうして決められ、軽量鉄骨とパネルで製作されました。
カプセルは直方体の1辺で柱に取り付き、残りの5辺は他と干渉せず宙に浮いています。外観の印象と異なり高度に独立した静謐な空間で、高速道路を走る車の音も聞こえません。
室内は6畳ほどの広さでベッドとユニットバスがあり、ほかに壁面収納式の机やテレビ、エアコン、物入れ。歩き回れるスペースは2畳もないでしょう。床面積にして10㎡、足を踏み入れた誰もが一瞬ひるむこの狭さは、極小の居住空間といわれます。
それなのにしばらく居ると心が落ち着くのです。なぜでしょうか。
直径1.3m、カプセル全体のスケール感からしても大きめな丸い開口が、高層ビルや首都高速道路といった最都心の風景を切りとっています。この窓と幾何学的な白い壁に囲まれると、なんだか宇宙船のコクピットにいるよう。ここはマンションの一室ではなく東京という宇宙に浮かぶ秘密基地なのでは…イメージした瞬間、狭さの感覚が消えました。
円窓に魔法をかけられたのかもしれません。異空間にスリップするがごときこの非日常性、カプセルタワーの真髄がここにあります。
円窓は開閉できない“はめ殺し”。カプセルはエアコン完備だから窓を開けての換気は不要、というわけです。寝起きはできても調理設備はなく、カセットコンロで料理すれば湯気やにおいがこもり、扉から廊下に流れ出ていくのを待つしかありません。
光を取り入れて外を見る。2つの機能に窓は特化しているのです。ホテル的セカンドハウスやオフィス向けという当初の目的を考えれば、これも自然だったかもしれません。
時は流れ利用者が変わると、いくつものカプセルが住居として使われるようになりました。それでも食事は外食やテイクアウト。銀座という街をダイニングや冷蔵庫として使うのが、受け継がれるカプセル暮らしの流儀なのです。通年でのエアコン使用も同様で、皆がそれを受け入れています。
こうして円窓は純化され、宇宙船の開口であり続けました。多くの利用者がこの窓を愛してカプセルに身を置く実感を託し、合言葉のように“秘密基地”や“宇宙船”と口にします。
それは単に“丸くて大きいから”ではないはず。円窓はレトロフューチャー=永遠の未来を象徴するカプセルタワーの象徴です。そこからは、時空を超えて銀座を浮遊する自由な自分自身が見えるのではないでしょうか。
※2021年7月、中銀カプセルタワービルは老朽化により解体が予定され、利用者は全員退去しました。現在、カプセルを取りはずして美術館への寄贈や宿泊施設として改修・再利用するプロジェクトが進められています。